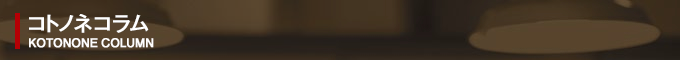【NPO法人シェルパ古市貴之 連載コラム】楢葉町でぽくりぽくり 泉のような拠り所
泉のような拠り所
先日「アレクセイと泉」と言う映画を観た。「自分の生まれた土地で役に立つことに意義がある。だから、ここで暮らしている」と主人公のアレクセイは言う。チェルノブイリから180キロ離れた村人の強制避難、そして地図上からの村の抹消。しかし、10数年後、その地には避難せず住み続けている高齢者とたった一人の若者アレクセイが暮らしていた。キノコなどは食べてはいけないと言われているけれど、食べずにいる方が病気になるという父の言葉に悩みながらキノコを採りに行く。なぜそこに住み続けるのか。それは、放射線が測定されない湧き水の泉があるからだと言う。その水で飲食をまかない、生活の全てをその泉が支えている。まさしく命の泉だ。映画を観終わった後、震災前よく汲みに行った故郷の山道の湧水を思い出した。
アレクセイの住む村はとても豊かな場所だと思った。買い物は月に何回か来る移動販売車に頼る生活で、自給自足のような生活であってもだ。異物を排除するのではなく、全てを受け入れる懐の深さがある。出来ないことがあれば出来る誰かが助けてくれる。自然とも協調するような関係性、コミュニティがあった。震災前の楢葉町もそんな地域であったに違いない。人口約7000人。たとえ福祉サービスが少なくても、ご近所の目があり、声かけがあり、自助や公助だけでなく互助で支えあってきた。もちろん、避難した地域で成熟したサービスに触れ、便利さを感じていることもあるかもしれない。それでもこの地域で、時には面倒なしがらみという繋がりが、実は大きな生活の支えだったことは、地域が崩壊し家族の在り方が変わってしまった現在、その有難さを深く痛感するところではないだろうか。復興や五輪という飽くなき前進のニュースがメディアを賑わす風潮の中で、宮沢賢治が言う「ほんとうの幸(さいわい)」とは何かを考えさせられる。
障がいを持たれる方や高齢者の生活を支えるには、医療や福祉サービスが欠かせないのは事実だ。しかし、地域の再構築が始まったばかりの地域に、単に既存の仕組みをドンと取り入れようとしてもすぐにマッチングするとは限らない。地域性を評価しながらも課題の共有や具体的な実践を行う過程を大事にする観点がなければ押し付けの地域づくりになるのではないか。用意された型にはまってもらうしかない地域。そこに「ほんとうの幸」はあるだろうか。住民が少ない地域、働き手の少ない地域においては、マンツーマンのホームヘルパー派遣や訪問看護などのサービスを創出するのは経営的には難しい。しかし一人ひとりに親身に寄り添おうとすれば必然的に個別対応となる。枠にはまってもらうのではなく、その人の大きさに寄り添う地域性の定着、永続的な体制保持につながる仕組みづくりがこの地域にも当然必要だ。
例えば、自宅に暮らしているかのようであり、医療も介護も受けられる仕組みとしての、シェアハウス的存在が、この地域には必要になるのではないか。全国的には、ホームホスピスとして実践されている例がある。そのような家単位の仕組みができれば、家族と離れて暮らすことになっても、安心してこの町で故郷で生を全うする選択肢になりうるのではないか。日本中どこに住んでもどんな境遇でも、一人ひとりにとって泉のような拠り所があるということ。幸とはそのようなことなのかもしれないと震災後思うようになった。
これまでのお話は、コチラ
【NPO法人シェルパ古市貴之 連載コラム】楢葉町でぽくりぽくり 今こそ賢治さん