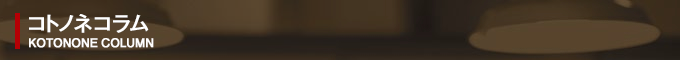「利用者」も「支援者」もなく働ける「理想郷」めざして――「なのはな村」(前編)
一組の夫婦がつくった小さな「理想郷」は、やがて地域に根づき、障害者が働き暮らす場として成長した。それは「家族」が、「組織」に変化した過程でもある。そして今また、その「組織」は、次のステップを探しつつある。宮崎県都城市で有機無農薬の農業を中心に事業展開する社会福祉法人なのはな村を訪ねた。
隠れ里のような農場の光景
大雨の中、農場への道すがら。社会福祉法人なのはな村の理事長・藤崎芳洋さんが車を停めて指さした先の畑で、ひとり黙々と作業をしている人がいた。今日スーパーに納品する分の大根を50本、抜いている。なのはな村のスタッフ、村山さんは41歳。若いころは南米を旅したり、自由きままに過ごしてきたという。30代の終わりに、故郷の都城に戻ってきて、古民家で居酒屋をはじめた。今は、平日は、なのはな村を手伝い、居酒屋は週末だけの営業。「ライブをやったり、自由に楽しんでるみたいですね」と藤崎さん。
気づくと、村山さんがゆっくりとこちらに向かってきた。もうずぶ濡れ、だけどニコニコ顔。「いやー、大変ですよ」なんて言いながら、どこか楽しそう。
木々に囲まれた農場に着いた。周りからは閉ざされて、隠れ里のよう。雨だからか、時間の流れがゆっくりに感じる。今日は畑仕事はお休み。作業場の大きな庇の下で、村山さんがとってきた大根を、みんなで洗う。鶏舎から、雨の中小走りに走って持ってきた卵を、きれいに拭きあげていく。静か、というわけではない。誰かの話し声と、雨がトタン屋根を打つ音が、ずーっと聞こえている。でも、なぜか、気持ちが落ち着く。藤崎さんが、誰かといっしょに、土砂降りの畑へ出て、収穫作業をしている。何十年も、毎日、変わらずに繰り返される光景。そんな気がした。
30年前、コミューンとしてはじまった
宮崎県都城市にある、社会福祉法人なのはな村の原型は、藤崎さんが30年前に夫婦二人ではじめた「コミューン」だった。「当時は日本中にそういう機運があふれていました。若い人たちが次々とコミューンを立ち上げて」。1985年に野草社から出版された『もうひとつの日本地図』をバイブルに、数多くの若者が、さまざまな地域で共同体を立ち上げた。その中には、障害者との共生をうたう共同体も、少なくなかった。「昔からコミューンとか共同体の運動に興味があって。高校を卒業してから東京に出て、精神病院でアルバイトをしていたんです。そのときに、アルバイト仲間と、障害者を入れたコミューンをつくりたいね、なんて、飲みながら話していて。30歳を前に結婚して実家がある都城市ではじめようと、戻ってきました。最初は福祉施設に入って、経験を積んで」。
贅沢しなけりゃ、生きられる。それでいい
以前から長崎では「なずな園」というコミューンが活動していた。障害者と家族のようにいっしょに暮らす「なずな園」をお手本に、自分も都城で障害者と共にコミューンをつくりたいと立ち上げたのが、なのはな村だった。養護学校の先生をしていたお母さんを説得して、藤崎家で所有していた山林を譲り受け、そこに障害者と共に農業をし、生活をする場所をつくった。野菜と鶏卵の生産・販売が主な生業で、鶏卵は近所に宅配もした。
「やってみたら、贅沢をしたいとか、もっと欲しい、と思わなかったら、十分生きていけるな、と思ったんです。畑があって、鶏がいて。みんな(障害者)は配達ができないけど、代わりに僕が市内に売りに行けばいい。その間、みんなは草取りなんかをして。あまり多くを望まなければ食べていける。それでいい、と思っていました」。余った作物は、漬物などに加工して売る。それくらいの規模でずっと回っていけばいい。そのやり方で、15年間続けた。最終的には、10人の障害者と共同生活を送るまでになった。
わたしたちがいなくなったら、どうなってしまうのか
しかし、藤崎さんに転機が訪れる。「50になったときに、もう辞めようかと思ったんです」。それは、藤崎さんがお手本にした、長崎のなずな園に起こった出来事がきっかけだった。なずな園は、藤崎さんと同じように、夫婦二人でやってきて、二人とも70代に差し掛かった。共に暮らす障害者も、70代になった。そんなとき、奥様が体調を崩し、入院することになった。その話を聞いて、藤崎さんは考えた。「これまで家族として共に生きてきたけど、支えるわたしたちがいなくなってしまったら」。きっと別々に、施設へ入ることになるのだろう。でも70歳になるまで、施設を知らずに生きてきた彼らは、どうなってしまうのか。「もちろん、やれるところまでやって、それでおしまい、というのも人生だから、それでいい、という考え方もあるかもしれません。でも、わたしたちはいいけれど、彼らはそれではいけないんじゃないか、と思って」。
藤崎さんは悩んだ末に、辞めるのではなく、なのはな村を社会福祉法人にすることに決めた。「私も都城に戻ってきた当初は、社会福祉法人で働いていましたから、社福がどんなものかはある程度はわかります。正直、自分の考え方とはずれているのではないかと、抵抗もありました。しかしここで、わたしたちがいなくなっても、きちんと回る組織をつくる必要があると決断しました」。
社会福祉法人なら、20人以上の障害者を受け入れなければならない。これまでの、10人を支えればよかった事業のやり方を変えなければいけない。そこから、なのはな村の農業は変わっていく。
※「なのはな村」の記事は、2015年8月発売の『コトノネ』15号に掲載されています。
写真:岸本剛