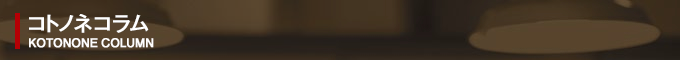「何気ない自由」を描く、街のアーティスト。―リベルテのいま(前編)
長野県上田市のリベルテの武捨友香さんが、ある日上田名物みすゞ飴を持って、編集部に遊びにきてくれました。古本の買取と販売をしているバリューブックスの中村和義さんと、スターバックスの山田朱香さんもいっしょです。
長野県内で、何やら「本」を使ったおもしろそうな取り組みがはじまっているとのこと。
バリューブックスのブログに、この取り組みやリベルテさんについてまとめた記事があるということで、早速コトノネWebに転載、ご紹介させていただくことになりました!
*************************
鮮やかな刺繍を施されたバッグ、味のあるレコードのブローチ、米袋を利用した手のひらサイズの小銭入れ。豊かな感性を細やかな手仕事で表現したアートの数々。しかし、これらを手がけるアーティストは皆、共通の問題を抱えている。
それは、“障害”を持っているということ。
NPO法人〈リベルテ〉では、「何気ない自由」や「権利」を尊重し、落書きにもみえてしまうような表現活動を”アート”として発信することで、自分らしくいられる居場所作りを行なっている。
ひとりの”表現者”として
上田駅から歩いて15分。かつて城下町として発展した北国街道・柳町は、ベーカリーや酒屋、蕎麦屋など古い長屋を利用した店が連なり、休日には多くの観光客で賑わう。そんなノスタルジックな風景の一角に、〈リベルテ〉が営むアートスペースはある。
時刻はお昼の12時を過ぎ、取材にきた旨をスタッフに伝えると、「もうすぐお昼ごはんの時間なので、ぜひ一緒に食べていってください」とうれしいお誘いが。靴を脱ぎ、案内されるまま奥のテーブルへ。コロッケ、もやしナムル、冷静スープ、料理が次々に運ばれてくる。リベルテでは毎日、その日いるメンバーとスタッフで揃ってお昼ごはんを食べる。地元の食材や有機野菜を使った日替わりのメニューは上田市内で店を営む〈食季café展〉によるもの。はじめは言葉なく、もくもくと箸を進めていたメンバーも、次第に緊張の糸がほぐれたのか、しゃべったり、笑ったり、ふだんの賑やかな食卓を見せてくれた。食後は描いた絵を見せあったり、みんなでパソコンの画面を覗き込んだり。その光景はまるでひとつの家族のようだった。
「“支援する側”と“支援される側”という関係には、ちょっと違和感を感じるんです。街のなかで一緒に暮らす仲間として、その人がやりたいことや、望んでいることができる環境になるように、僕らは支援活動をしています。だからといって、どちらが偉いとか、弱い立場とかはなく、あくまでフラットな関係でいたい」
そう話すのは、リベルテの代表を務める武捨和貴さん。もともと福祉とは縁遠い世界に生きてきた彼が、NPO法人を立ち上げるまでに至ったのは、一枚の絵がきっかけだった。
「関西の大学を卒業後、地元・上田市に戻ってきました。美術の勉強が好きだったので、アート系の仕事をしたいなと思っていました。いざ職を探し始めると地方にはアートに関わる仕事がほとんどありませんでした。今でこそ、NABOや犀の角があったり、デザイン関係者が東京からUターンで戻ってきたりしているけど、当時は経験を活かせる場所がどこにもなかった」。
「そんな時、たまたま行った喫茶店で展示されていた作品に衝撃を受けたんです。鮮やかな女性の絵でした。画用紙全紙サイズくらいの大きなその作品は、60代後半のおばあちゃんが描いたというから、さらに驚きました。ご本人に会ってみたくなって訪ねたのが〈風の工房〉。ものづくりを通して、障害者の方々の自立を支援する場所です。そこでスタッフの方からボランティアに誘われ、気づけばそのまま就職していました(笑)働きだしてから、その作家の方と僕の関係は利用者とスタッフというより、師匠と弟子。もちろん僕が弟子です。そんな関係は僕が施設を離れるまで、約8年間続きました。よく画材が用意されていないと叱られたりして、厳しかったですね。その方は今年になって亡くなってしまったんですけど、80歳近く記憶も曖昧になるなか、唯一、僕の名前だけは覚えていてくれました。すごく感謝しているし、作家として今でもリスペクトしています」。
はじめて触れる福祉の世界では、単純に“支援する側”と“支援される側”という関係ではなく、作家とスタッフという関係性のなかで絆を深めていった。リベルテはその延長線上にあるのだと武捨さんはいう。
声なきコミュニケーションのかたち
「風の工房は街から車で30分かかるような山の中にありました。メンバーの半分以上がそこで生活をし、残りのメンバーはスタッフが毎日車で送迎していました。会話が困難な人が多く、表情や短い発語のなかから、どんな考えや行動を希望しているかを読み解くことが日常。けれど彼らも、絵や写真を前にすれば、一般の人と同じように感動するし、自分で絵を描く人もいた。直接的なコミュニケーションをとるのは難しくても、創作活動を通じてなら、街の人々ともコミュニケーションがとれるんじゃないかと考えるようになっていきました」。
街には自立したい、働きたい、という気持ちがあっても、自分の持つ障害が社会との“摩擦”となり、「生きづらさ」を抱える人は少なくない。そんな人々の居場所を作るため、今から約5年前に武捨さんは〈リベルテ〉を立ち上げた。あえて街の中心にスペースを作ったのは、できるだけ自分たちの力で通える場所にしたかったから。彼らが創作活動をするアトリエと同じ場所にギャラリーを設けることで、街の住人や観光に訪れた人々がNPOの目的を知らず、その作品を手にとり、購入していく。そこに言葉がなくとも、アートを接点に、街と人がつながっていく。
それぞれの生きかた。働きかた。
現在リベルテには40名前後のメンバーが契約している。一般的な福祉施設だと、毎日通う人の数は、利用者の半数以上を占めているそう。一方、リベルテでは毎日通う人の数は全体の1割ほど。週3、4回のペースで来る人が多く、なおかつ活動や仕事ができる時間も2〜3時間くらいだという。活動資金は1日あたりに利用する人数に応じて入ってくる。持続的な運営や、お給料をもらって働くスタッフのためを思えば、利用者にはできるだけ毎日通ってほしい。でも、障害の特性上、活動の限界時間が短いというメンバーの事情もある。行きたくないのに無理やり通わせるのは、ちょっと違う。
「そのバランスは難しいです。ずっと葛藤しています。ただ、リベルテで起きている問題って、地域の問題でもあるんです。毎日決まった時間働くのが難しい人っていうのは、どんな街にも必ずいます。いわゆる生産性のない生き方だとしても、お互いに許しあえる関係性があれば、そこからまた新しいものを生み出せるはず。ふつうとは違う働き方や、地域活動のモデルにリベルテがなれればいいなと思います」
武捨さんは、経営者としての苦悩をあえて、スタッフにも共有している。社会の問題として一緒に考えてもらうためだ。そんななか、スタッフの佃さんは、リベルテの目指す社会についてこんな風に語った。「今日は働かない、と自分で選択するのも大切。自分のペースに合わせた働きかた・過ごしかたを探していくことも大事なこと。リベルテのなかで起きていることは、タイミングによっては正解にもなりうる」。一方、武捨さんの妻であり、スタッフの黒岩さんは、なかなか来てくれないメンバーに、3つのギャグを送ったら、久しぶりに顔を出してくれた。「心を掴んだのでしょうね」と武捨さんは笑う。
「ぼくらの支援は一般的な支援とは少しずれているかもしれない。障害者でも働こうとか、障害者の人のためにがんばろう、ということより、 “ともに地域のなかで生きていこう”ということを大切にしています」。
Written by 北村 有沙
Photo by Yukihiro Shinohara
後編につづく