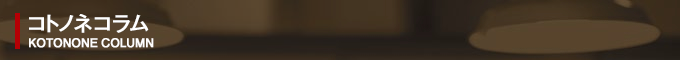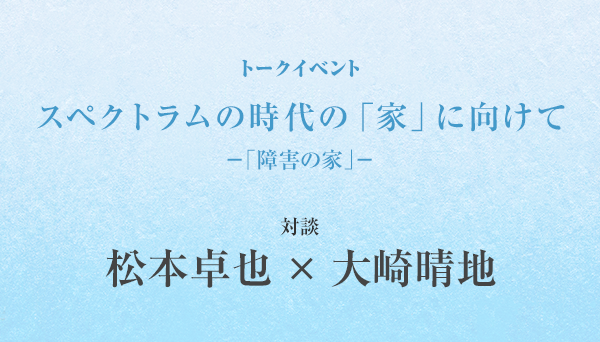スペクトラムの時代の「家」に向けて ー「障害の家」松本卓也×大崎晴地 トークイベント中編「肯定だけで、作られた家」
肯定だけで、作られた家
大崎 僕がなぜ建築のほうに接近してきたかといえば、松本さんが仰ったように「リハビリ」という視点においても必然的だったのかもしれません。言語や文学、芸術というよりは、どんどん共存するための技法として、建築という日常環境の側からその人の現実を考えていく、個人の内面を設計する方向に向いているんです。
photo by Takahiro Tsushima
たとえば荒川修作(※6)が、障害という言い方はしていないですけど、傾いている床だったり、体に負荷を与えるような建築を作ったりしている。荒川さんは三鷹天命反転住宅で最終的には私的な生活空間そのものを、ある意味では真のユニヴァーサルにしたということが言われるんですが、ちょっと違うなと思い始めていることがあって。それは時代的なパラダイムの違いというのがもちろんあって、ダダイズムから荒川さんは始まっていて、何か「意味」に対する無意味みたいなもの、否定性みたいなことがすごく強く言われた時代に、何も意味しない行為の働きをダイアグラム化していた。もともと分析哲学の言語ゲームなどを身体の手続きに置き換えていくようなところがありますからね。破壊的、否定的な部分は、性格的なところでの荒川さんの言葉や思想というものには現れているけれども、同時に作り上げられるものは割と幾何学的で心理学的、認知心理学的な要素がすごくある。初期の意味の仕事は「建築する身体」というコンセプトに結実していきますが、それはいわゆる建築家の言う「建築」ではない。言語と建築の乖離みたいなことが起きていたと思うんです。それは建築分野においても現代思想の脱構築とかが流行していた時代に、一つのメタファーとして見られるところがあった。つまり、言語的な脱構築だけじゃなくて、建築においても脱構築的な建築のモデルが目指されていたような時代があったわけですよね。
でも今、否定性とか破壊みたいなことよりも、荒川さんの住宅はヘレン・ケラーに捧げていることにも現れていますが、一つのユニヴァーサルなモデルを社会に提示しているようにも思える。これはデュシャンの非網膜的なレディメイドの観念が、目の見えないケラーの身体を通じてダイアグラム化していく過程に出てきています。対して、障害の家はスペクトラムの時代に、もともと人それぞれの建築のあり方があってもいいんじゃないか、と。そうすると「建築する身体」のような行為に対して、もっと無媒介にモノそのものに触れて作り上げていく方法というか、大事なことは、いかに実装しながら個別の方法をそれぞれが確立していけるかだと思うんです。それこそ別に発表するでもなく、自分で建築を作ってしまうアウトサイダー的な建築の文脈もあって、そことはもうちょっと線引きしたいというのがあるんですけど。
photo by Takahiro Tsushima
松本 その荒川さんの話は非常に面白いですね。つまり、荒川さんの場合は既成の「正常性」なり「意味」なりに対する「反転」が問題になっているわけですよね。あらゆる価値の転換がダダ的なものと結びついているのだけれども、そうすると、「正常」な住みやすい家から、「不自由」な住みにくい家になるわけですよね。でも、この「障害の家」はちょっと違うコンセプトなんですね。
ある障害をもっている人にとってはこの状態が一番住みやすい、一番しっくりくるということがコンセプトとしてある。荒川さんのやっていることが、脱構築や言語的な媒介に引きずられたかたちで既存の「正常性」をひっくり返そうとするものであったとすれば、この「障害の家」はそのような否定性にもとづくものではなくて、自分自身の個別性がそのまま建築で表現される、肯定性の建築という感じがします。
言葉では、どうしても理解できない
松本 言葉で他者の体験を理解する際には、どうしても理解できないことが残る。むしろ、その理解できなさという否定性によって何かを理解するという考えがかつてはあった。しかし、この「障害の家」に自分の身を置くことによって得られる体験は、言語を媒介として物事を考えるモデルから離れることを可能にしてくれるのかもしれません。
今、現代思想のなかでもそのような流れがありますね。クァンタン・メイヤスー(※7)は、これまでの近現代思想が、カントの物自体と現象という区別に代表されるように、世界にはどれだけ頑張っても接近不可能なものがあって、人間はそのような不可能なものが整序されたかぎりのものしか認識しえない、という考え(相関主義)にもとづいていたのに対して、むしろそのような立場から離れて、たとえば物自体そのものを直接的に取り扱うことを試みています。そのような思想のなかでは、他者とは無関係に、自足的にあるような実在が問題となっている。この「障害の家」もそのような思想と共鳴する要素を、障害という身体のバリアの芸術として提示しているのかもしれません。
かつてハイデガーは、「言葉は存在の住処である」と言っていました。ラカンもまた、人間は象徴界という言葉の世界のなかに棲まうことによって「正常」な人間になると考えていました。逆説的な言い方になりますが、おそらく大崎さんがやっていることは「住処は存在の住処である」という、ともすれば同語反復と思われがちなテーゼを立てたときに可能になる、ある種の他者との伝達や理解の可能性を追求されているのではないでしょうか。
ちなみにラカンにも、言語を媒介として物事を考える立場から徐々に離れていく流れがあるんですよ。ラカンは、言語によって媒介された主体形成を強調したことで知られているけれども、後期の70年代は、むしろ身体において何が生じているかということを問題にしていて、そこでは普通の言語(ラング)ではなく「ララング」という身体の次元に衝撃ないしトラウマとして与えられる言語が扱われている。ラカン理論の変遷を考えても、言語を媒介として考えている時期から、言語を媒介とせず身体ないしララングで考えている時期への移行がありますが、大崎さんがさきほど言われた荒川さんとご自身の違いという点は、そこに対応するように思いました。
大崎 建築ってやっぱり割と理論的なものとの相関ってすごく強くあると思うし、フロイトが建築をモデルにして深層と表層みたいなことを話している議論があって、そういったものをうまく現代ヴァージョンみたいなものに考えられると面白いと思うんですよね。