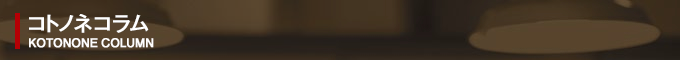「自分が『昇天していく』くらい、おもしろい仕事」―大垣勲男さん(後編)
ほかの地域に先駆けて、「地域移行」が進んだ北海道伊達市。
人口3万5000人の町の中で、約600名の知的障害のある人たちがサポートを受けながら暮らす。町を歩くと、障害のある人を実際よく見かける。伊達コスモス21で働くある職員さんは、伊達に引っ越してきてまずはじめに、その町の様子に衝撃を受けたと言う。「4月1日にはじめて出勤するときに、この人もきっと障害者だ、この人もきっと障害者だっていう人が道にたくさんいらして。それにすごいびっくりしたのを覚えています。あと、休みの日にダイソーとかお店に行くと、やっぱり障害のある人がいっぱいいるんですよね。最初はそれにも驚きました」。
はじめは障害のある人たちが町に買い物に行くと、店員さんが引っ込んでしまって物を買うこともできなかったという時代から、いまでは、ときにレジで店員さんにお財布を渡せば必要なお金をとって、おつりをお財布にしまってくれる、そんな光景も自然と見かけるようになった。
障害者が、市民を変えていく
伊達コスモス21の常務理事、大垣勲男さんは言う。「1つの結論だと思うんですが、どれだけ講演の上手な人を呼んで福祉の市民フォーラムを開いて、ジーンとくる話を聞いても、1週間で忘れちゃうのが大半だと思うんです。だから障害のある人が1人でも多く、町の中で生活する、そして市民が関わっていく。これしかないと思うんです。伊達の町を変えていったのは、障害者です。福祉従事者が24時間365日支えているように見えますが、確かに最初はそうでしたが、いまは彼らを包み込んだり、支えているのは、市民なんです。市民といっても、いろんな市民がいます。雇用主という市民だったり、障害者といっしょに働く市民だったり、隣に居合わせた住民である市民だったり。その市民が抱く不安不審を先取りし、払拭して安心感に切り替えながらメリットに切り替えていく、実はそれがわたしたちの仕事ですね」。
取材をしていくうちに、伊達の町ほど「障害者が生きやすい町」はないだろうと思えてくるが、大垣さんにはずっと心にとめている言葉がある。
「昔、ある方に『大垣、伊達が地域福祉を語るな』って言われたんです。わたしは職業青春をかけていろんなことをやってきたつもりでした。だけどそれは本物の地域福祉じゃないって言われたんです。30代後半のときかな。そもそも太陽の園に入所されている方々は、全道各地から、ふるさとを離れて来ているんです。家族からも友達からも親戚からも。それをふる里に帰さず、入所施設のある町に人工衛星のように増やしていく、それが地域福祉かって。確かにそうなんです」。
福祉の仕事は「犠牲」じゃない
最後に大垣さんにどうして福祉の仕事を志したのか、聞いてみた。「一昔前までは年間5日くらいしか休まなかったですし、帰るのも深夜でした」というほど、大垣さんは、福祉の仕事に打ち込んできた。家族に障害のある人がいるわけでもない。どこからこんな情熱が来るのか、不思議だった。
「わたしは北海道の剣淵町出身、隣が和寒町なんです。和寒町に塩狩峠という峠があるんです。それで高校2年生のときに、タイトルが気になって、三浦綾子さんの『塩狩峠』を読んでしまったんです。自ら車輪の下になって、乗客を救ったっていう実話を元にした小説なんですが、全然ストーリーを知らずに、なんの気なしに手にとって、読んでしまって。もう涙が止まらなかったですね。それから、自分の中に命題ができました。人のために自分を犠牲にできるのかと。当時は犠牲という言葉だったんですが、それがきっかけでしたね。自分が一生懸命働いて、人の役にたったり、つらさが軽減されたり、それが福祉だと思って、それで福祉系の学校に進んだんです。ただ、頭が悪いからか、30歳を過ぎるまではわからなかったですね。犠牲ではなかったんです。自分のベストな状況で、自分の1個の命で多くの人たちを救うという、いわば成就であり最高の自己実現だったと思うんです。
それは自分もそうですよね。家族と出かける時間もほとんどとれなかった、じゃあわたしが犠牲になっていたか、っていうとそうじゃなくて、やりたいことを信念持って、具現化していく、それは自己実現であり、すごく楽しいこと。自分が昇天していくというか。それぐらいおもしろい仕事だって思います」。
この話には後日談がある。大垣さんの娘さんが高校生のとき、読書感想文の本としてたまたま、『塩狩峠』を選んだ。書いた感想文を読むと、「主人公は犠牲になったのではない」、と娘さんが書いていたのだと言う。大垣さんは自分の話を一切したことはなかった。「あれにはびっくりしましたね」。
※『コトノネ』19号の特集で社会福祉法人伊達コスモス21の取り組みをご紹介しています。
写真:渋谷文廣