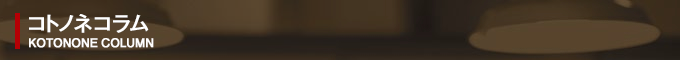【コトノネ編集長のおまけ日記】「捨ててない、拾ったのだ」
※映画の結末が出てきます。
是枝裕和監督の『万引き家族』。カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞作品だもんね、観ておかなきゃ、と、嫁はんと出かけた。観終わって映画館を出るなり、嫁はんは顔をほころばして、「よかったね」と言った。どうかな、とわたしはつい口に出した。「なんで」。嫁はんがとがめ口調だった。「いやあ、ただシンドかった、ずっとシンドかった」。是枝監督の『誰も知らない』もそうだった。「でも、安藤サクラ、よかったやないの」と嫁はんは気を取り直して言った。「ほんま、ほんま、うまいね」とわたしは返した。安藤サクラは表情ひとつで映画のすべてを語っている気がした。夫治のリリー・フランキー、妻信代の安藤サクラ、祖母初枝の樹木希林、信代の妹亜紀の松岡芙優、それに子どもの少年。みんなすばらしい。それに、近所の団地の廊下で、家から追い出されていた少女を治が見かねて連れ帰って、家族に加わる。家族は、初枝のか細い年金を頼りに、足らずを万引きでしのいでいる。最下層に近い暮らしだ。万引きは、治と少年の仕事。貧しいが、笑いはある。笑いがあるが、ほほえましいか、こころ温まるか、と言えば、そうではない。ほとんどは、散らかった家と万引きのシーン。社会から排除された匂いが、いつも立ち上っている。それがリアリティをもって描かれている。だから、シンドイ。
突然、異色のシーンが登場する。家族そろって海水浴に出かける。絵にかいたような家族。海辺で、治、信代、亜紀、少年、少女が仲良くはしゃぐ。シアワセそうな家族の後姿。これが、唯一、白々しい、ウソくさいシーンだった。
このシーンを合図に、映画は急ピッチでラストに向かう。少年は、いつも万引きをしていた駄菓子屋で、はじめて少女にやらせる。柄本明が演じる店主が、帰ろうとする少年を呼び止めて、2本のチューブのジュースを差し出して、「いいかい、妹にさせたら、だめだよ」と言う。みんな見抜かれていた。まっとうな社会秩序が少年にくさびを打つ。
次にその店に行くと、忌中の張り紙が貼ってある。少年はその足でスーパーに行き、ばれるように万引きをする。捕まる。家族ごと警察に捕まる。
死んだ祖母を家の床下に埋めたこともばれる。刑事は、なぜ、捨てた、と問い詰める。信代は答える。「捨てたのではない。拾ったのだ」。この家族は、誰ひとり血のつながりがない。信代が「拾ってきた」家族だった。ほんとうの家族から捨てられ、社会からはじき出された人たちを、信代が集めてきた。
信代は刑務所に入り、治は、たぶん生活保護をもらったのだろう、小さなアパートでのひとり暮らしになり、少年は施設に引き取られ、少女はほんとうの両親のもとに戻る。2カ月間も捜索願を出さなかった親の元へ。やっと社会の秩序は守られた。しかし、その秩序の内側は壊れているのだ。薄皮の社会秩序なんか、もう破れた方がいいのではないか。
「あんた、そんだけ、話すのは、やっぱり、ええ映画やったんや、ないの」「そうかもしれん。そうやな」。けど、やっぱり、シンドかった。