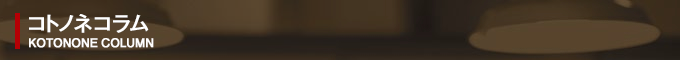17年間精神科病棟を見続ける蓄積が、ぼくには必要だった ―写真家・大西暢夫さん
『コトノネ』26号の巻頭グラビアを撮影いただいた写真家の大西暢夫さん。
2018年2月練馬文化センターで開催された大西さんの写真展「ひとりひとりの人 -精神科病棟取材17年の記録」は、2日間の開催にも関わらず、500人を超える人が来場しました。
そもそも、どうして精神科病棟での写真を撮りはじめたのか、普段どんな風に撮影しているのか、大西さんに話を伺いました。
「顔が見える」ことを前提にしたかった
― 精神科病棟で撮影をはじめたのは、どんなきっかけからですか?
単純な話なんですけれども、ぼくはフリーのカメラマンで、雑誌(『精神科看護』)から依頼があったんです。32、33歳のとき。
バックナンバーの目次を見ると、「地域に根ざした医療」って、書いてありました。「地域」はぼくたちのことだなぁと思ったんです。でも正直なところ、このままでは精神科の患者さんを知ってくれと言っても伝わらないな、と思いました。
とにかく顔が映っていない。患者さんが映っていたとしても、カメラマンがすごい気を使って、後ろから撮っている。それで、引き受けるときに、顔が見えるということを前提にしたいという話をさせていただいて。患者さんも、看護師さんたちも映っている、そんなページをつくっていきたいんだっていう話をしました。
― それまで福祉の世界と、接点はあったんでしょうか?
ぼくは写真家で映画監督の本橋成一氏のアシスタントをしていたのですが、本橋さんの娘がダウン症だったんです。赤ちゃんのときから、ぼくは面倒を見ていました。小学校高学年になるまで、ずっと家族のように生活していて。それがぼくの中では大きかったかもしれません。
まぁ当時精神障害は、障害者認定されていないころでしたけど。
そこから17年間、1号もかけることなく、精神科病棟での撮影を続けています。最近は病院から、撮影してほしいとオファーがあるんです。時代が変わったなぁという気がします。すごくうれしいですね。目指していたところもあったので。
足りないのは、日常会話
― はじめて精神科病棟に行ったときのことは、覚えていますか?
覚えています。古い病棟だったので、鉄格子があって。そのときにショッキングな光景がありました。コンクリート打ちっぱなしの保護室。冷たーい床ですよね。そこで、うんちをもらしてしまった患者さんがいた。60半ばくらいの人。その人が素っ裸になっていたんです。たぶん洗うためだったんですけど。それを若い20代の看護師さんがホースでじゃーって水をかけていたんですよ。患者さんはわーっとわめきながら、自動的に体が洗われちゃうような状態。すごいショックでした。患者さんではあるけれど、この人にもいろんな歴史あるのにって。いまでもかなりこびりついています。このまま、これを常識と思っていっていたら、人間扱いしなくなると思って。
長期入院っていう言葉も撮影をはじめてから、知りました。患者さんが当たり前のようにタバコを吸っていたり。5時半になったらだーっと廊下に並んで、みんなでいっしょにごはん食べている。普通の病院は、ないじゃないですか、精神科ならでは。そこから長期入院ということを、テーマに置くようになりました。
― 撮影はいつもどんな風に?
最初は編集部の人といっしょに行っていましたが、いまはもう、現場に1人で行っています。だいたい2日間、ずっと病棟に入っています。休憩をとることもなく、ずーっと患者さんといますね。連載ももう長いので、病院から信頼してもらえて、鍵をもらって看護師のようにジャラジャラさせながら病棟の中を、自由に行き来させてもらうこともあります(笑)。
2日間、しゃべり倒しますね。仕事モードでっていう感じでもなく、普通のおっちゃん、おばちゃんとするみたいに。あの人たちにいちばん足りないものって、たぶん日常会話だと思うんですよね。でも、人としていちばん必要だと、ぼくは思っている。やっぱり看護師さんは忙しいので、無駄な会話はなかなかできない。今日はタバコ2本までだからね、とか。10くらいしか会話の種類がないような感じがある。無駄な会話っていうのを自分はいちばん大事にします。
そのうち、すこーしだけなんですが、彼らが求めていることがすこーし見えてくるんです。
たとえば、新聞の広告を見てて「兄ちゃん、今日卵安いねんけど」って話しかけられる。そこから話が展開して、実は卵料理、好きやったねん。子どもがこういうの好きでなって。そういう中で、入院生活のつらさみたいのが垣間見えていったりとか。そういうことを拾い上げていく。
なんとなく会話をして、シャッターをきるのは翌日にしておいたりしますね。最初はじーっと見られるだけで次の日に、兄ちゃん昨日どっか飲みにいったんって話しかけられて、あの店に行きました、そうかそうかって話ができることもある。
全部妄想でも、いいじゃない
― 「写真館」というページでは、1人の患者さんについて深く掘り下げていますね。
患者さんだって、家族がいたり、その人が歩んできた道があるのに、長期入院が続くとそういうことはほとんど言葉にならなくて、病気だけの付き合いになっていく。なので、このページは、病院名も個人名も全部出して、鈴木さんなら鈴木さんのことを1人の人間として書くっていうページなんです。
だいたい1時間くらい、2人っきりで面会室で話を聞きます。真面目な患者さんはいつ病気になったとか、そういったことを箇条書きにされてくるんですけど、ぼくが聞くことはそこに1つもない(笑)。いつ病気になったかなんて聞きたいとは思っていないんです。
いきなり恋人の名前はなんだったのって聞いたりします。ぼくはそっちの方が聞きたいんです。どんな仕事をしていたのかとか。同じ年代なら同じものを見ているわけじゃないですか。その感慨深さもあるし。
話されたことが全部妄想だったりしますけど、そのままぼくは書くんです。すごくステキな妄想だったりするんですよ。たとえばある方は、子どもの話をされました。でも結婚もしていない人で。結婚したい願望がすごく強かった人だったんですよね。そういうことが妄想の中に飛び出てしまった。でもすごいいい話だったんですよ。それを否定しちゃダメだなと思って、その話にゆだねて、そのまんま書きました。ああ大西さん、見事に騙されてますって看護師さんに言われるときもあるし、逆に全然看護師さんも知らない話だったりすることもあります。
― 患者さんと支える側のスタッフさんを、ずっと間近で見てきたんですね。
精神科病院のスタッフの人たちの、長期入院されている方を退院させていくための努力っていうのは、もうほんとうに涙ぐましいものがあって。自治会に行って土下座して、患者さんを退院させたいから、このアパートに住まわせてくださいって。ここまでやるのかって思いました。
でも自治会から、きちがいは困るからってばつんと言われてしまう。そういう姿を何度も見て、これだけ努力してて、ここまでやってるのにって、すごく悔しい思いを持つ。それでやっぱり退院を断念して、っていうのを見ていくと、間口をどんどん狭めたのは誰だって。
もしかしたら長期入院を生み出したのは、精神科ではなくて、ぼくたちと違うかって。ぼくたちが狭めたことによって、精神科がやむを得ず患者さんを引き受けている。 その思いが根底にある。だから、言い返せる力が必要なんです。それには、どれだけ見ているかっていう蓄積が、ぼくには必要で。これ以上のものはないと思っているんです。
精神障害も途中で障害者になったり、退院を促進させたり、この17年で時代がぐるぐる変わったし、そういう変化をまたいでこれたなって。いまはもう精神科病院といっても、鉄格子のイメージないですよね。
ぼくがおじいさんになったころは長期入院っていう言葉が壊滅しているかもしれない、しているといいなと思うんですけど。過去にこんなことがあったんだって、教科書に出てくる、そんな風になるといいなと思っています。
★季刊『コトノネ』26号刊行を記念して、6月23日(土)に下北沢の本屋B&Bで、大西さんが監督したドキュメンタリー映画『オキナワへいこう!』の上映会を開催します。
2月に練馬で行われたこの映画の上映会は、キャンセル待ちの方もでる盛況ぶりでした。大西さんにもお越しいただき、お話いただきます。
下記B&BさんのWebから、お申込みください。
http://bookandbeer.com/event/20180623b_kotonone/
お待ちしています!