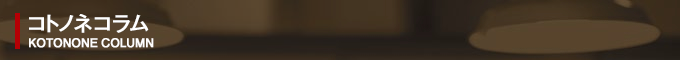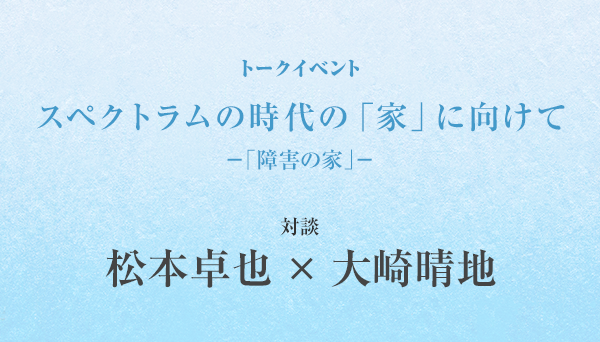スペクトラムの時代の「家」に向けてー「障害の家」松本卓也×大崎晴地 トークイベント前編「今は、誰もがプチ狂気をもっている時代」
2018年3月9日(金)〜30日(金)まで、東京・墨田区にてアーティスト大崎晴地さんの「障害の家」プロジェクト第3弾「HYPER-CONCRETENESS―フィクションと生活」が開催されます。
「障害の家」は、2015年に大崎さんが建築家の笠島俊一さんと始めたプロジェクト。障害のある人が健常者の社会に合わせるかたちとなっている「バリアフリー」の現状に対して問題を提起し、「障害」や「バリア」のある生活のほうが豊かで多様であることを検証する活動です。最終的には実際の「家」を建てることを目指しています。今年度の開催に合わせ、昨年3月20日に行われた、精神科医の松本卓也さんとの対談の模様をお届けします。
※2月21日発売のコトノネ25号の「アートが目ざめる」でも、「障害の家」プロジェクトをご紹介します。
トークイベント風景(会場:千住たこテラス)photo by Takahiro Tsushima
「障害×建築」を考える
大崎 今日は京都大学大学院人間・環境学研究科准教授の松本卓也さんにお越しいただきました。松本さんはジャック・ラカン(※1)の研究者でもあって、その難解な精神病理学の分野の研究をかなり整理されたかたちでまとめた『人はみな妄想する』(※2)という本が評判になりました。
僕とは、精神病理学や病跡学の繋がりがあって、松本さんが編集協力で関わった『atプラス』(太田出版)の「臨床と人文知」特集号(2016年11月刊行)に僕も寄稿しました。
「障害の家」プロジェクトは2015年に始まって、今回が2回目の発表です。1回目は「障害の家」というテーマ、コンセプトが先にあって、いくつかのアイデアをマケットと設計図に落としたものを発表しました。今回はここ北千住のコミュニティスペース・たこテラスで等身大の空間における「障害のある家」という、実際の生活空間を想定できるような発表になったと。実際に一軒の「障害の家」を設計するということを想定してこのプロジェクトを進めていて、さまざまな場所で実験的にケーススタディしていこうと思ってます。
『atプラス』では、「障害と建築」というタイトルで論文を書いているのですが、もともと僕は脳損傷、脳の変容によって知覚や経験が変わるという事象への関心から始まっていて、リハビリテーションの現場に関わりながら芸術との関わりについて考えています。近年は、その背景を歴史的、批評的にたどるために精神病理のほうに関心が向いてきました。美術はシュルレアリスムもそうですけど、人間の深層構造をいかに表現に反映できるかといった、精神分析と密接だった歴史があるわけです。現代美術の歴史の上でもいろいろ考えたいことも多いんですが、まず話したいことは、精神病、統合失調症という病気が20世紀の現代思想の概念モデルとして提示されてきたということがあって。現代では統合失調症が減ってきていて、自閉症にシフトしてきたということが、臨床と人文知のなかで大きく掲げられている。松本さんが、これまでは垂直的な狂気みたいなものとして、統合失調症があったけれども、今は誰もがある種、小さな狂気、プチ狂気のようなものをもっていると書かれていますが、障害と健常という境がうまくつかなくなっている、スペクトラム(※3)化したというパラダイムの変動がある。そうした時代背景があって、いかにこういうコミュニティスペースや地域のなかで芸術や臨床を問題提起できるのかということは、すごく密接な問題だと思います。そのあたりから話ができたらいいなと思うんですが。
障害と健常の境が、うまくつかなくなっている
松本 建築や住宅は、人を特定のかたちに作り上げる、つまり社会のなかで良いとされている「人間」に人を作りかえるという側面がありますね。フーコーが紹介した監獄における「パノプティコン」のシステムもそうです。
今日、僕がこの「障害の家」を見て、一番はじめに思ったのは、これは秘密基地だな、ということです。小学生ぐらいのとき、山のなかに捨ててある畳を拾ってきたりして、その上にいろんなものを置いて、ここは誰のスペースで向こうは誰のスペースだとか、線を引いたりしましたよね。そういう場所があった感覚を思い出して懐かしい気がしました。
「段畳」photo by Takahiro Tsushima
さきほど大崎さんのほうから、「隠喩としての病」の位置にある病理が、かつての統合失調症(昔は精神分裂病と呼んでいました)から、徐々に自閉症のほうに移っているというお話がありました。哲学や現代思想などの人文知や、あるいは芸術にも、そのような時代の変化があるのかもしれません。
この2つの時代の大きな違いを決定しているのは、正常性を前提としてそれに対する逸脱ないし侵犯として異常性を考えるパラダイムと、そもそも正常性なるものは存在せず、誰もがスペクトラム化された「プチ狂気」なのだと考えるパラダイムの違いではないでしょうか。一昔前の時代は、正常性というのがはっきりと示されていた時代でした。つまり、学校でちゃんと教育されて「まとも」な大人になる、というような正常性が一方にあって、そういう人々は精神医学や精神分析の世界では「神経症者」と呼ばれていました。他方、「精神病者」と呼ばれる人々は、そのような正常性からの逸脱形態だったわけです。
かつての反精神医学は、そのような正常と逸脱の対立に対して抵抗した思想です。つまり、既存の精神医療のシステムというのはある特定の人たちを「正常」として、その枠内に収まらない人に「精神病者」というラベルを貼って排除し、さらには精神病院に閉じ込めたり、「正常」の側に近づけようとしたりしている、と考えるのです。普通、精神科以外の医療においては、医師か患者かのどちらかが拒否すれば治療は行われませんが、精神科では患者が拒否しても、医師が必要だと判断すれば治療(強制入院)が行われる、という非対称的な構造が今だにあります。反精神医学の論者たちは、そのような構造を告発し、「狂気」をめぐる価値転倒をもくろんでいたのです。
かつて、統合失調症が論じられる際に採用されていた目線は、基本的に「悲劇モデル」でした。つまり、ひとたび統合失調症という過程(プロセス)が始まってしまうと、基本的には完治することはなく、急激ないし徐々に進行していくと考えられていたのです。もちろん、その過程のなかではそれなりに社会適応ができる人もいますが、一回始まってしまったら過程がずっと続いていき、最終的には人格機能が解体するというモデルで考えられていたんですね。
統合失調症が「悲劇の病」として隠喩化される前には、同じく「不治の病」とされていた結核がその位置を占めていました。そこから、結核文学が生まれます。悲劇化されると、文学のテーマになりやすいんですね。ただし、統合失調症の場合は、その悲劇モデルのなかにもう一つ捻りがある。つまり、統合失調症という「不治の病」になることは悲劇なのだけれども、その患者さんは、悲劇と引き換えに何かしらの「真理」に触れている、と考えられたのです。これはカール・ヤスパースが病跡学の古典である『ストリンドベリとファン・ゴッホ』のなかではっきりと主張している事柄ですが、つまり統合失調症を病むということは確かに悲劇的なのだけども、それと引き換えに、何か人間の深い真理に触れる芸術作品を作ることができるようになる、統合失調症という狂気はそのような意味での天才性と関係している、と考えられたわけです。草間彌生みたいな人を想像してもらうとよいでしょうか。要するに、かつての時代は、統合失調症という逸脱のなかに「真理」を見出し、その「真理」をつねに「正常」の側に回収してきたのです。
みんな「プチ狂気」をもっている
松本 ところが、現代では、精神障害をそのような悲劇モデルで見ることはかなり少なくなりました。なぜかといえば、社会の変化もそうですが、統合失調症という病それ自体が軽症化し、回復しやすくなったことがあげられます。かつては統合失調症について「治癒」という言葉はあまり用いられませんでしたが、現代では寛解(※4)やリカバリーという言葉がよく使われるようになりました。昔は、統合失調症といえば入院治療しかありませんでしたが、今では外来に通いながら普通に社会で生きていける人がほとんどです。このような時代に、統合失調症を悲劇モデルで見る視点がかつてと同じような仕方で機能することはできません。
「振動する建材」photo by sachiho inoue
2000年代になると、いわゆる「発達障害」、特に自閉症に大きな注目が集まりました。自閉症の現代的な概念にみられる一つの特徴は、障害を「スペクトラム」として考えるところです。もともと「自閉症スペクトラム」という言葉を使いはじめたのは、ローナ・ウィングというイギリスの精神科医で、彼女はいわゆるカナー型の自閉症と、アスペルガー症候群は実は虹のようなひとつづきの連続的なスペクトラムであるということを実証しました。さらに現代では、自閉症に見られるような特徴は、薄められたかたちで、誰もがちょっとずつもっているんじゃないかと考える発想が広まってきているようです。すると、「自閉症」かどうかは、単にそのグラデーションの閾値以上なのか以下なのかという問題にすぎないことになる。かつての時代には、「精神病」というラベルを貼られた人々が排除され、そこに見出された「真理」が「正常」の側に回収されてきたわけですが、世のなかにはいろんな濃度でいろんな障害をもった人がいると考えることが普通になると、特定の障害を悲劇的にメタファー化する必要もなくなってしまう。それが、現代における大きな変化の要因の一つではないかと思っています。
こうなると、かつての時代において議論されていた、いわゆる「正常」とそこから排除された「狂気」のあいだの非対称性、つまりどちらが権力をもつのか、あるいはどちらに主導的な価値があるのか、という問題は生じ得なくなります。むしろ、多様な「プチ狂気」だらけの社会のなかで、それぞれがどのように共存するのか、あるいはどのようにその「プチ狂気」をコントロールするのかが問題になってくるわけです。おそらくは今後数十年でその傾向ははっきりとしてくるでしょう。
大崎さんが『atプラス』で書かれていた論文も、おそらくはそのような観点で書かれているのではないでしょうか。統合失調症の家族モデルを「家」に転用して、その患者さんを「家」という問題から考えてみると、かつての「家」は「正常性」を押し付ける装置であり、統合失調症はそこから外れるもの、つまり「家」に住めないから精神病院に入院せざるを得なかったと考えることができるでしょう。それに対して、自閉症者というのは「はじめから家がない、あるいは自分の輪郭さえ定まらない」人々なんだ、という言い方を大崎さんはされている。これは非常に面白い話です。かつてのような「正常」とそれに対する「逸脱」という仕方で「家」や精神病を考えているかぎりは、家にちゃんと住めているのかいないのか、という対立になるのですが、しかし自閉症というモデルから見た場合、どう自分の住まいを作るのか、ということが問題になってくるわけなんですね。はじめから家がないからこそ、自分で住みやすいようにセルフビルドで作っていく。大崎さんはそのような発想をもっていらっしゃるのかなと感じています。