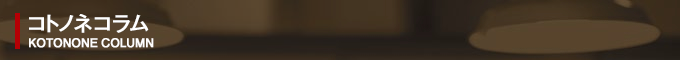コトノネだらだら座談会 のぞき見版【11月28日 三枝七都子さん】
11月「だらだら座談会」のトーカーは三枝七都子さん。三枝さんは、7年間理学療法士として病院に勤務した後、大学院へ進学し、「多様性」や「富山型デイサービス」について研究をしています。なぜ、進学の道を選んだのでしょうか。
三枝さんは、大学を卒業した後、地域医療の病院で、理学療法士として働きはじめました。そこは、高齢者と話すことが多い職場だったそう。幼少期に、ベネズエラ、アメリカ、そしてサウジアラビアへ移り住み、さまざまな慣習の中で過ごしてきた自分を『中途半端な日本人』だと思っていた三枝さん。母国への違和感を持ちながら生きていたと言います。「人生の先輩」として患者さんの話を聞くうちに、いろいろな生き方があることを知り、支えてもらうこともありました。しかし、病院の中にあるリハビリテーションの制度では、その人たち自身の人生を支えてあげたいという想いを実現することが難しいと感じるようになりました。病院を辞め、大学院へ進学。理学療法士として、また研究者として、リハビリテーションの在り方と向き合うことになりました。
「このままでいいのかなって思っていることがあって…」と三枝さん。「リハビリテーション」の従来の意味は、人が自分の持っている機能を取り戻していくというもの。けれど、地域の中で障害者や高齢者を支えていく「地域リハビリテーション」と呼ばれる概念も、近年知られるようになりました。病院の中から、地域まで、さまざまな場面で求められるようになったリハビリ専門職の人たち。しかし、地域で働く専門職の研究については、「こうあるべき姿」論ばかりが先行していて、実情から議論されている例は少ないのだそうです。三枝さんは「専門職が地域の中で働きかけていくには、どのような視点が必要なのか」という課題に対して、仮説を立てます。それは、「専門職の人が、個人ではなく、場に働きかけて、活動に関わる人を巻き込んでいく仕組みをつくっていくことが必要なのではないか」ということでした。
その裏付けとして、三枝さんが研究しているのは「富山型デイサービス」。(『コトノネ』vol.20でも特集しています。)障害者も高齢者も職員も「ごちゃまぜ」に、ともに在宅生活をする形をとっています。ある施設では、「リハビリ」を強要しなくても、半身まひの人が、片手で子どもをあやしていたり、高齢の利用者が、料理が苦手な職員を放っておけなくて手伝ってくれて、結果「リハビリ的」なことができてしまう。なぜ、そのようなことが起こっているのか。「理学療法士でもある、その施設の理事長さんの視点をうかがっていて、その理由は『専門職たりうる人が持つ目』にあったんじゃないかと感じたんです」と三枝さん。理学療法士に限らず、作業療法士、言語聴覚士など、「リハビリ専門職」と呼ばれる人たちは、相手の動きや、身体の形、座り方などを見て、その人の能力を見定めるようなトレーニングを受けています。一般的には「何もできない」と判断されてしまう患者さんがいても、彼らは、その人の「できること」を判断して、「できる」環境を整えていくことで、「場に働きかけることができる」そう。その取り組みが持つ意味は、単に機能回復の介助をすることではなくて、その人の在りようにも触れるような、もっと広い意味を持っていることなんじゃないか、と三枝さんは言います。
三枝さんは、「日本独自のリハビリテーションのあり方」を模索していると言います。「福祉先進国」と呼ばれているスウェーデンでは、「その人がどうしたいのか」尊重してもらえる環境があります。しかし、自主的に声をあげることが求められます。一方で、日本の「草の根的」にはじまっている取り組みでは、「その人が何をしたいって言えなくても、周りの人たちが、いろんな関わりをすることで、その人の主張が見えてくる」ことがあるそう。「個人」対「個人」の単一的な関係の中で主張を聞きだすのではなく、多様な関係性の中で、当事者の声を可視化していける環境こそ、目指していくものかもしれないと、三枝さんは言います。「主体性を出すように迫るのではなくて、みんなとの関係の中で、本人の主体性みたいなものがやんわり共通認識できる世界が、この『富山型』にはあって。これって、日本独特のものなんではないかって思うんです。スウェーデンとは違って、日本だからできることなんじゃないのかなって」。(三枝さん)
現場で何かが起こっている。きっと、現場の人は気づいているはず。けれど、研究となると、裏付けて証明していくことは簡単ではありません。理学療法士として現場を知っている立場であり、研究者としてそれを証明していく立場である三枝さんの葛藤と、それでも進んでいく熱さが見えたような気がしました。