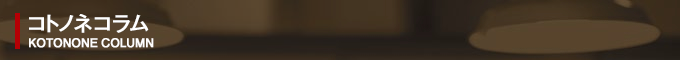この人たちが、これから歩いていく道を整備しなければ――「多摩草むらの会」(前編)
「多摩草むらの会」の事業を、一言でまとめるのは難しい。幾つもの事業所があり、そのそれぞれがまったく異なる事業をしていて、そのどれもが高い収益をあげ、あるいは地域で必要とされている。しかし、代表の風間美代子さんに話をきくと、「草むらの会」が、ただ利益や規模の拡大を目指しているのではないことがわかる。
できる人もできない人も、それぞれの仕事を
京王堀之内駅から徒歩で30分ほど。多摩地域の里山風景がいまも残る、まさに夢のような場所が「夢畑(ゆめばたけ)」だ。ここが東京か、と思うばかりの、のどかなで緑深い場所。里山の中には小川が流れ、季節になるとホタルの姿も見ることができる、という。
この日も、何人もの障害者が働いていた。ある人は畑の草むしり。またある人はハウスの中の菌床しいたけの世話。あちらこちらに生えているハーブを摘んでいる人もいるし、山野草を摘んで、テーブルフラワーにする役目の人もいる。
お昼前になると、ワゴン車がやってくる。就労継続支援B型事業所「遊夢(ゆうむ)」でつくられたお弁当が配られる。ぶどう棚の木陰に作った休憩所で、みんなでお弁当を食べる。ここでは、それぞれがそれぞれのペースで作業をする。体力がある人は、太陽の下で汗を流す。陽の光が苦手だ、という人は、ハウスの中で、しいたけの世話をすればいい。通っているうちに体力も気力もついて、いろんな仕事をやりたくなった、という人には、そのための仕事がある。調子が悪く、あまりきつい作業はしたくない、という人にも、できることはある。
利用者は、スタッフにも、講師にもなれる
「夢像(ゆめぞう)」は、松が谷団地の中、商店街の空き店舗を利用して作られたパソコンサロンだ。何十台ものパソコンの前で、利用者がパソコンの使い方を、それぞれのペースで学んでいる。ワード、エクセルの使い方を学んでいる人もいれば、HTMLを学ぶ人もいる。システム構築の経験が有る人は、高度な言語を独学で学んでいる。ここで学んだ技術を活かして就労に結びつける利用者もいれば、地域の高齢者などを対象にしたパソコン教室の講師として活動する利用者もいる。利用者から「夢像」のスタッフになる人もいる。スキルを身につけた利用者には、それを活かす場所が用意されている。
おいしい饅頭と、本格派のカフェと
京王堀之内駅の近くには、「まんじゅう屋 遊夢」がある。「夢畑」でとれた大豆を使った「大豆あん」が特徴の、大きなまんじゅうが名物。製菓の確かな技術が評価されて、銀座の人気和菓子店「銀座かずや」とのコラボプロジェクトにおいて、東京・青梅のゆずを加工し、ジャムにする作業を担当することができた。
多摩センター三越の6階には、レストラン「畑deきっちん」がある。飲食店街の一角に、他の飲食店と並んで、自然食を中心としたメニューが特色のカフェを構える。「森」をイメージしたという、木と緑に覆われた、A型事業所とは思えないような本格的な内装。素材は「夢畑」でとれた作物が中心。野菜の販売もしている。利用者は、ホールでもキッチンでも働いている。
東京・多摩地区で精神障害者の支援事業を展開するNPO法人「多摩草むらの会」には、いくつもの顔がある。里山を活かした農業。商店街の空き店舗を活かし、地域に貢献するパソコン教室。高い技術を持つまんじゅう屋。自然食の本格カフェ。他にも輸入生地を加工した手芸ショップ、清掃業務など、実に幅広い。地域も多摩市、八王子市、さらには東京都新宿高田馬場と、複数にまたがっている。
「多摩草むらの会」の、地域的、事業的な広がりは、しかし実は理事長・風間美代子さんの、たったひとつの、切実な思いからスタートしている。
「精神に障害を持つ人たちの、進んでいく道を整備しなければ」。
卵のように壊れる、と息子は言った
風間さんの長男が、統合失調症を発症したのは、彼が大学浪人中のことだった。「息子は本当に親になんの心配もかけない子で。そのままだったらきっと、私は子育てに成功した親だ、と傲慢になっていたと思います」。思い返してみれば、発症の前兆はあった。「暴走族が攻めてきそうだ」と言ってみたり、雑誌に自分のことが載っているんじゃないか、と言ってみたり。「高校は進学校でしたから、ほかの生徒は3年生になったら部活を辞めるんですが、うちの子だけ続けたりと、引っかかる点はありました」。そのうちに引きこもるようになった。父親とはまったく話さなくなり、風間さんと、妹さんの声にしか耳を貸さなくなった。
この話をすると必ず思い出すのは、この時期の長男の言葉だ。
「あるとき、居間で新聞を読んでいると長男が2階から降りてきて、冷蔵庫から卵を取り出すと、私のとなりでぽこっと割ったんです」。どうしたの、と風間さんがきくと、長男は「いや、僕はきっとこういうふうに壊れていくから、もうお母さんには何もしてあげられないかもしれないよ」と言った。
また別のときには「お母さん、僕は深海魚になったのかもしれない。急に上がったらきっと眼が飛び出て死んじゃうから。ゆっくり上がっていくから、待っててね」と言った。「きっと私が病院の先生に相談していたのを敏感に感じ取ったのでしょうね」。
その二つの言葉によって、風間さんは「いままで私がいい思いをしてきた分、今度は私が支える番だ」という思いを強くした。
子どもを救うには、親から離す
その後、急性の症状が襲い、長男は入院を余儀なくされた。「私が襲われると思って、通行人に危害を加えそうになったんです」。病院にいってはじめて「統合失調症」の病名を知らされた。帰りのバスの中で涙が出たが、同時に「泣いている場合じゃない」と覚悟を決めた。覚悟を決めたら、体が動いた。本屋にいって、統合失調症についての、あらゆる本を買った。つてをたどって、何人もの先生に話を聞いた。「完治しない、って言われたんです。完治しない病気なんてあるのか、と思って」。動くうちに、いろんなことがわかってきた。ある先生からは「精神障害の当事者も親も、団結して行政に要望を伝えることをしない。だから他の障害に比べて、精神は30年遅れている」と言われた。なにをしているんだろう。一番つらいのは本人のはずなのに。親は悲しんだり苦しんだりしている場合じゃない。息子がこれからの長い人生を歩いていく道を整備するには、息子のことだけを考えていたのでは、とても無理だ。
風間さんは、まずグループホームを作った。「とにかく彼らを、親から離したかった」。精神障害のほとんどは中途障害。親は「良かったころ」の彼らが忘れられない。そのためちょっと調子がよくなると「ちゃんと朝起きたら」とか「作業所に行ったら」と干渉してしまう。親子の距離が近いと、お互いに疲れてしまう。安心できる「居場所」を確保することからはじめた。
※「多摩草むらの会」の記事は、2014年8月発売の『コトノネ』11号に掲載されています。
写真:岸本剛