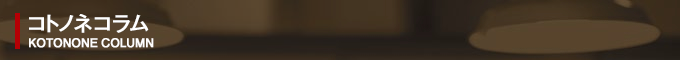味噌づくりが、からだにスッと入っていく――「片山商店」(前編)
京都府亀岡市で半世紀の歴史を持つ味噌蔵「京丹味噌 片山商店」で、6年前から障害者が働いている。自分たちの得意を生かして、味噌づくりを、自分たちのものにしようとしている。
人の目と手が入った、昔ながらの味噌づくり
京都市内から30分ほど、亀岡市に、味噌づくりの仕事をする障害者がいると聞いて、訪ねた。「京丹味噌 片山商店」は、半世紀の歴史を誇る味噌蔵だ。社長の片山秋雄さんが起こした。中学を卒業してすぐ大手の味噌メーカーに入って15年ほど勤めた秋雄さん。自分の作りたい味噌がある、と独立した。高度経済成長期。ものはバンバン作れば作っただけ売れた。でも秋雄さんは、大量生産ではなく、少量で多品種、そして品質にこだわった味噌づくりがしたかった。「会社はなかなかこっちの思いに沿うてくれへん。そやったら、自分の思うとおりにやればいいんやないかと思うて、はじめたんです」。会社に勤務していた時から応援してくれるお客さんの中には、料亭のお得意さんを持つ人もいた。「こういうものを作ってくれ、これやったら売れると、そういう要望を聞きながらええもんつくったら、勝手に商売できるで、と言われて」。以来50年、「優れた商品を作れるところが最後は残る」と、基本的な味噌づくりの手法は変えずにやってきた。特に味噌の味の決め手となる麹づくりの工程はどうしても機械化・自動化できない。蒸した米に麹菌を振りまぜ、杉室で発酵させるが、一昼夜、2時間ごとに確認しなければならない。手間と時間をかけ、人の目と手で確認しながらの作業を、ずっと続けてきた。こうしてできた高い品質の味噌は、京都市内のみならず東京の料亭、和食店などで高い評価を受け、その味を知った舌の肥えたお客さんも、全国から味噌を買い求める。
片山商店で味噌づくりを担当しているのは、社長の片山秋雄さん、二代目で専務の片山宏司さん、それに田中博一さんと中澤由美子さんの二人。田中さんと、中澤さんには、知的障害がある。本来はもう一人、健常のスタッフがいるというが、取材時にはけがをしていて休みだった。しかしよく考えると、社長親子以外で味噌づくりを担当するのは、ほぼ障害者だ。片山商店のまさに中核である味噌づくりを、障害者が担っている。
もくもくと、しかし、しっかりと
さっそく味噌づくりの様子を見せてもらう。作業場では、大豆を煮る作業を行っていた。大きな釜をかたむけると、中からたくさんの大豆があふれてくる。それらを要領よくコンテナに移し、そこから撹拌機に入れていく。味噌の原料となる大豆を煮て、すりつぶす作業が行われる。あふれ出る大量の水を浴びながら、しかし黙々と作業している。見ていると、コンテナに残ったほんの少しの大豆も残さず、丁寧にすくい上げている。四人は、あまり声をかけあったりはしない。ときどき「ホース、お願いします」とか「じゃ、次いこうか」などと、最低限の声かけをしているだけだ。なんとくお互いがなにを考えているのか、次に何をしたいのか、それぞれ分かり合っている、という感じだ。
言葉はいらない。アイコンタクトで十分
大豆の作業が終わると、今度はトラックに乗って、できたばかりの味噌を、倉庫へ運ぶ。すりつぶした大豆と麹、それに塩を合わせたものを、味噌蔵で熟成させることで、味噌ができあがる。作業場でつくられた味噌の「原型」を、倉庫に運び、木樽の中で熟成させるのだ。ここは田中さんと中澤さんの二人が担当する。小さな、といっても、一人の力ではとても運べないような大きさの、味噌がたっぷり入ったプラスチックの樽を、トラックに積み込む。田中さんは器用に樽を回しながら移動させていく。積み終わると、田中さんの運転で、車で五分ほどの倉庫へ。「もう何年ものかわからない」という巨大な六つの木樽が収められた倉庫は、味噌の香りが立ち込めている。田中さん、今度はフォークリフトで樽を運ぶ。樽運びは田中さんに任せて、中澤さんは、麹を発酵させるドラムの水洗い。専務の宏司さんは「このドラムの操作は難しくて、僕と中澤さんしかできないんですよ。彼女は機械の操作が得意なんです」と笑った。
再び作業場に戻って、今度は麹づくり。ドラムで加熱した米麹を広げて、杉室で発酵させる準備。ドラムから米麹を取り出し、コンベアに乗せて、杉室で広げる。四人は、誰も何も言わないのに、それぞれの持ち場について、流れ作業をはじめる。息がぴったり合っている。宏司さんは「作業の段取りは決まってますから、現場であれこれ言わなくても大丈夫。ときどき『そっちいく?じゃあ、おれこっちいくわ』みたいにアイコンタクトしてますね(笑)。でも、それも全部の作業をわかってないと」。田中さんも中澤さんも、作業のことはよく知っているし、お互いなにを考えているか、よく読んでますね、と言う。
※「片山商店」の記事は、2015年11月発売の『コトノネ』16号に掲載されています。
写真:河野豊