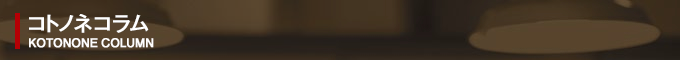「もう障害者だけ、幸せになる時代じゃない」―大原裕介さん(後編)
北海道当別町にある社会福祉法人ゆうゆうは今年、12年目を迎える。
「福祉施設は、特にこういう地方では、町のインフラとしての財産ですから。町が疲弊していっている中で、建物やマンパワー、ノウハウを共有財産として、どうやって町の人たちとシェアできるかっていうことを考えていかないと」と理事長の大原裕介さん。
「地域を創る」を掲げ、10年間走り続けたゆうゆうは町にどんな変化を生み、これからどこへ向かっていくのだろうか。
何も起こらないことに、感動する
「当別町で、うちがいちばん新卒をとっている法人なんですよ」と、大原さん。今年の春も7人の新人スタッフを迎えたゆうゆう。北海道内だけでなく、全国から就職希望の若者が集まる。職員の平均年齢は20代後半。札幌から車で1時間という立地、高齢化・人口減が続く農業が基幹産業の町であることを考えれば、若い移住者は町にとって、何にも代えがたいものだろう。さらに全国からゆうゆうの取り組みを学ぼうと訪れる視察者の数は年間1000人以上。人の流れだけとっても、町にとってのゆうゆうの存在感がわかるが、10年間事業を続けてきたことは、数値にはあらわれない、何気ない「風景」となってあらわれはじめている。
10年経ってどんな変化がありましたか、と大原さんに尋ねると、こんな答えが返ってきた。「たまたまぼくが町で歩いているとき、うちの利用者さんの前から、小学生の子たちがわーっと来るのに、出くわしたことがあったんです。どうなるかな、すれ違うときによけたり、あとから振り返ったり、ひそひそ話をするかなって思って見ていたら、まったく何も起こらなかった。障害がある人を特別に思わなかったってこと。そういう小さなことに、感動しますね」。
そういえば取材中も、こんなことがあった。カフェで働く1人の障害者スタッフが、お客さんの子どものそばに「かわいいねぇ~」と言いながら、近寄っていった。その様子を、お母さんはニコニコと見ていた。大原さんはそのとき、何も言っていなかったが、あとからこんな話をしてくれた。
「10年前なら、お母さんはたぶん、危ないからごめんねとか言って、無意識のうちに、子どもを引き離していたと思うんです。障害者は何するかわからない、そんな風に思う人が多かった。それが今日は普通に見守っていた。ああいう姿を見ると、自分たちが昼夜問わず走り回って、答えが見つからないまま、だけどやることをやろうって言っていたときから続けてきてよかったと思います。こういう風景が増えていくのが、うれしいんです」。
誰も目立たなくていい
ゆうゆうの取り組みを聞いていると、障害者と支援者だけで成り立つものは、ほとんどない。近所のおじいちゃん、おばあちゃん、子ども、学生、主婦、あらゆる人たちが、どこかしらに関わってくる。そもそも、障害者だけがいる空間に、大原さんはずっと馴染めなかったのだと言う。
「これまでいっぱいいろんな現場を見ましたけど、障害者だけ、お年寄りだけ、っていうのを、どうしても異様だと思ってしまうんです。同じカテゴライズで束ねられた人が1つの空間にいると、たぶんそれだけで、違う人たちを排除してしまいますよね。なんというか、頑張れば頑張る分、結果的に障害のある人と地域との関係性というのを、ぼくらが遮断してしまっているような気がしてしまうんです。だから、いろんな人がいた方がいい、誰も目立たなくっていいんです」。だから、ゆうゆうの事業所は、障害者だけではなく、みんなの「コミュニティスポット」になることを徹底的に意図してつくられている。
支援する人とされる人という二者の関係性だけにならないことは、支援という視点からも必要だと大原さんは言う。「支援する人とされる人って、やっぱりどこまでいっても、対等じゃない。だけど、いろんな人が関わることで、その関係性に変化が生まれると思うんです。ほかの人がいることは監視の目にもなるから、ケアもしっかりやるようになる。もちろんいろんな人がいる場になじめない人もいるので、アセスメントがすごく大事なんですが」。
関係性の中で、人が可能性を伸ばしていくのだとしたら、支援者の仕事とは、一方的に手を差し伸べるのではなく、その人の可能性を信じ、環境を準備して、あらゆる人や機会との接点をただ、つくり続けることなのかもしれない。
10年経って、振り出しに戻った
当別町で10年前いちばん困っていた存在だった障害者は、いまではいちばん福祉的なサービスが充実している人になった。前編で紹介した「当別の障害者は幸せね」という言葉を、大原さんはただ喜んで受け止めてはいない。「ぼくこれは、非常にうれしかった半面、挑戦的な言葉だと思ったんです。障害者は制度の中にいて窮屈かもしれないけど、社会に守られている。一方で、制度でまったくサポートを受けられない、生きずらさを抱えた人たち、たとえばシングルマザーや、介護サービスを受けていない高齢者、診断を受けていない発達障害の人…。ぼくは社会福祉法人のあり方としてしっかりと制度サービスの中で収入や基盤を整備して、そこで出た余剰をそういった人たちの支援に、これからは使っていきたいんです」。
そしてこう付け加えた。「補助金もあてにできないし、行政にお金くれとも言いたくない。ちょうど学生のときに、レスパイトサービスをつくったときに戻った、そんな感覚がしてるんです」。
元に戻ると言っても、0からのスタートではない。大原さんたちには10年間培ってきた、障害者支援のスキルがある。1人ひとりの特性を見抜き、その人に合ったマッチングをしていく。その地道な積み重ねがあるからこそ、大原さんには自信がある。「障害者就労をやっているぼくらはもっと多様な人たちの働くことの支援をできると思っています」。
※『コトノネ』19号の特集で、社会福祉法人ゆうゆうの取り組みをご紹介しています。
写真:渋谷文廣